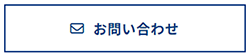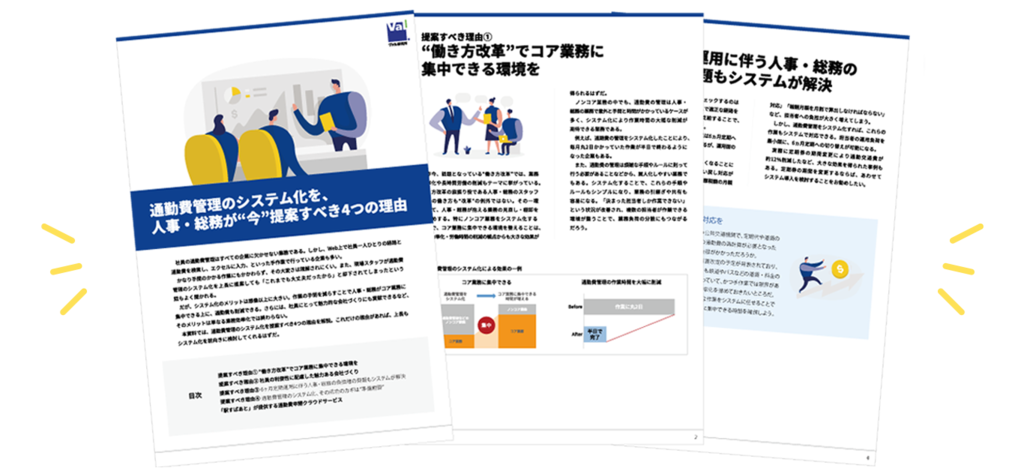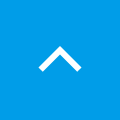通勤手当の不正受給対策とは?懲戒処分の判断基準と企業側の対策を解説

通勤手当は従業員の通勤費用を補助するための制度ですが、虚偽の申告や実際より高額な経路での申請など、不正受給が発生するリスクがあります。従業員の不正受給が発覚した際は、差額の返還請求だけでなく懲戒処分を検討しなければなりません。
本記事では、通勤手当の不正受給が発覚した際の懲戒処分の判断基準や、未然に防ぐための実務的な対策について解説します。
目次[非表示]
通勤手当の不正受給に該当する具体例
従業員が過剰に通勤手当を受け取っていれば、不正受給に該当する可能性があります。まずは、通勤手当の不正受給に該当する代表的な例を紹介します。
例1:実際は徒歩や自転車で通勤しているのに公共交通機関で申請
自宅から会社まで徒歩や自転車で通勤しているにもかかわらず、電車やバスを利用するとして虚偽の申請を行い、通勤手当を受け取るケースです。引っ越しを機に徒歩や自転車通勤に変えたものの、意図的に申請を行わないことなどで発生します。
例2:実際より運賃が高額で遠回りな経路で申請
通勤経路は複数あるものの、会社が定める「最も経済的かつ合理的な経路」ではなく、意図的に運賃が高くなる遠回りな経路や、特急料金などが含まれる高額なルートで申請するケースです。わずかな差額でも、長期間にわたれば大きな金額になります。
例3:引っ越ししたあとも通勤経路の変更を申請していない
引っ越しによって交通費が安くなったにもかかわらず、会社に通勤経路の変更申請をせず、以前の高い交通費のまま通勤手当を受給し続けるケースです。従業員が意図的に申請をしていない場合は、不正受給とみなされる可能性があります。
通勤手当の不正受給が発覚した場合の対応
通勤手当の不正受給が発覚した場合、会社側は従業員に対して一定の対応を行わなければなりません。ここでは不正受給が発覚した場合の対応策について、実務上の注意点を交えながら解説します。
差額の返還請求
通勤手当の不正受給が発覚した場合は、従業員に対して差額の返還請求を行うこととなります。もし、一括返済が困難であれば分割返済とするなどの対応も検討しましょう。
本人へのヒアリングを通じて事実確認を行い、不正受給の期間と金額を算出し、対象者に返還額や期限を通知します。また、賃金請求権の時効は通常3年ですが、不当利得返還請求権は原則10年(民法第166条第1項)であるため、時効成立していない期間については、請求が可能です。
なお、会社が一方的に給与から返還額を天引き(相殺)することは、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に違反する可能性があります。返還は、本人の同意を得て銀行振込等で受領するか、給与からの天引きについて本人の明確な同意を書面で得たうえ(労働契約法第8条)で行うようにしましょう。
参考1:e-Gov法令検索「民法」
参考2:e-Gov法令検索「労働基準法」
参考3:e-Gov法令検索「労働契約法」
就業規則に基づく懲戒処分の検討
一般的に就業規則には、服務規律に「不正をしてはならない」という規定を定めています。通勤手当の不正受給は、会社を欺き、不当に財産的利益を得る行為であり、服務規律違反に該当します。
そのため、会社側は就業規則の懲戒規定に基づき、従業員に対してけん責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇といった懲戒処分を科すことができます。ただし、どの処分を選択するかは、悪質性や金額などを考慮して慎重に判断する必要があります。
通勤手当の不正受給における懲戒処分の可否と判例の考え方
従業員の不正受給が発覚した際、人事担当者が最も悩むのが「どの程度の懲戒処分が妥当か」という点です。ここでは、対照的な結論となった2つの判例を比較し、処分の妥当性を判断するポイントを解説します。
【懲戒解雇が無効とされた例】光輪モータース事件(東京地裁 平成18年5月26日)
光輪モータース事件は、通勤手当を不正受給していた従業員に対する懲戒解雇が無効とされたケースです。
事件の概要
ある従業員が、転居後に転居前より低い交通費の通勤経路へ変更したものの会社へ届け出ず、約4年8ヶ月にわたり総額約35万円の差額定期代を受給していました。
会社は就業規則の懲戒解雇にあたる「虚偽請求による不正受給」を理由に懲戒解雇しましたが、従業員は地位確認と賃金支払いを求め提訴しました。
裁判所の判断とポイント
裁判所は懲戒解雇を「無効」と判断しました。その理由は以下の通りです。
- 悪質性:
詐取といえるほど悪質性は高くなく、事件発覚後に従業員が返金の準備がされている点を考慮 - 被害額の大きさ:
累積約35万円は高額とまではいえない - 処分の重さ:
会社側の懲戒権の範囲を逸脱し、重きに過ぎる処分と判断。ただし、減給や出勤停止等の軽減可能性を否定できない
裁判所は、これらの事情を総合的に考慮し、不正受給の事実は認めつつも、それに対する懲戒解雇という処分は重すぎであり「懲戒権の濫用(労働契約法第15条)」にあたると判断しました。
参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「通勤・通勤手当を巡る法的諸問題」
【懲戒解雇が有効とされた例】かどや製油事件(東京地裁 平成20年3月27日)
かどや製油事件は通勤手当の不正受給でありながら、懲戒解雇が有効とされたケースです。
事件の概要
ある従業員が、虚偽の転居届を提出し、約4年半で約231万円の通勤手当を不正受給していました。会社は就業規則に基づき懲戒解雇、不当利得返還請求を行いましたが、従業員は解雇は権利濫用として地位確認・賃金支払を請求しました。
裁判所の判断とポイント
裁判所は懲戒解雇を「有効」と判断しました。その理由は以下の通りです。
- 悪質性:
金額が多額かつ手口が計画的で詐欺的。企業秩序への影響も大きい - 被害額の大きさ:
不正受給額が約231万円であり、高額である - 処分の重さ:
会社の懲戒解雇処分は重過ぎず妥当。解雇権・懲戒権の濫用には当たらない
これらの点から、懲戒解雇という最も重い処分を科すことにも「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」と認められました。判例では、不正の態様が悪質で、会社に与えた損害が大きい場合には、懲戒解雇も正当化されうることを示しています。
この2つの判例からわかることは、単に「不正受給があった」という事実だけで解雇処分を決めるのは危険だということです。処分の妥当性は、不正の悪質性・計画性(故意か過失か)、期間、金額、本人の反省の度合いなどを総合的に比較衡量して、慎重に判断しなければなりません。
参考:全国労働基準関係団体連合会「かどや製油事件」
通勤手当の不正受給を未然に防ぐ対策
会社にとって最も重要なのは、不正が起こらない環境を整備することです。そのための具体的な対策を3つ紹介します。
ルールの明確化と周知徹底
不正が発生する背景には、ルールの曖昧さがあります。就業規則や通勤手当支給規程などで、「自宅から会社までの最も経済的かつ合理的な経路」を原則とすることを明記したり、 虚偽の申請が発覚した場合は、手当の返還義務が生じること、懲戒処分の対象となることを明記するなど、ルールを明確にして周知徹底することが大切です。
就業規則については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
コンプライアンス意識の醸成
従業員一人ひとりの不正受給に対する意識を高めることも対策の一つです。入社時研修で通勤手当のルールを丁寧に説明し、不正が重大な問題であることを啓発したり、社内報などで定期的にコンプライアンスに関するアナウンスを行うなどが考えられます。
「少額でも不正受給になる」「不正受給は懲戒処分の対象となる」ことを意識させ、コンプライアンス意識を醸成させましょう。
まとめ:不正受給を防止できる管理体制を構築しましょう
通勤手当の不正受給を防ぐためには、従業員一人ひとりの申請経路を確認し、適切な経路かを判断する必要があります。これは現場担当者にとって大きな負担です。従業員数が増えれば増えるほど、人の手では限界があるでしょう。
そこでおすすめしたいのが「駅すぱあと 通勤費Web」です。「駅すぱあと 通勤費Web」は経路検索エンジンを活用し、従業員の申請経路が合理的かを自動で判定します。これにより、申請から承認、経路チェックまでをワンストップで自動化し、ヒューマンエラーや見落としを防止できます。人事・労務担当者の負担を減らしながら、会社のコンプライアンスを守る強力なパートナーとして、ぜひ「駅すぱあと 通勤費Web」の導入をご検討ください。
詳しい資料はこちらからダウンロードいただけます。