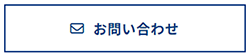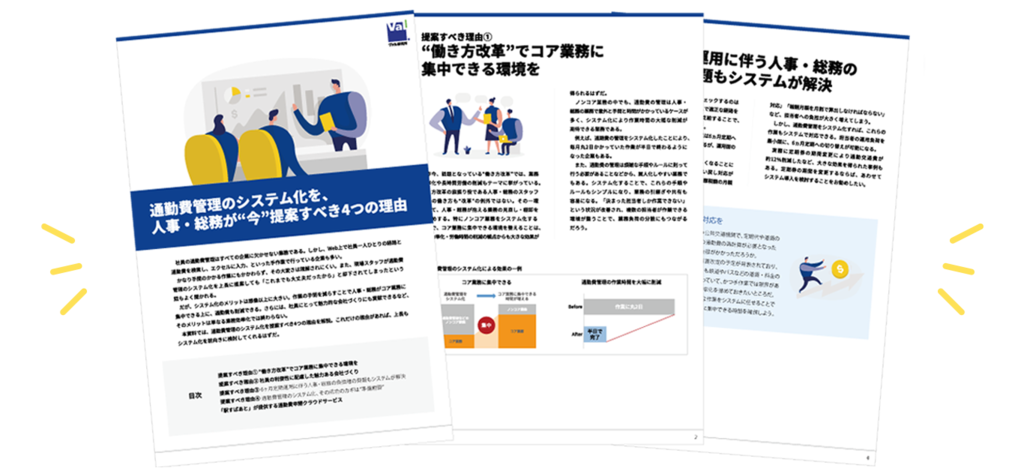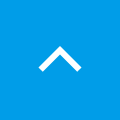通勤手当は就業規則にどう書けばいい?記載例とポイントを解説
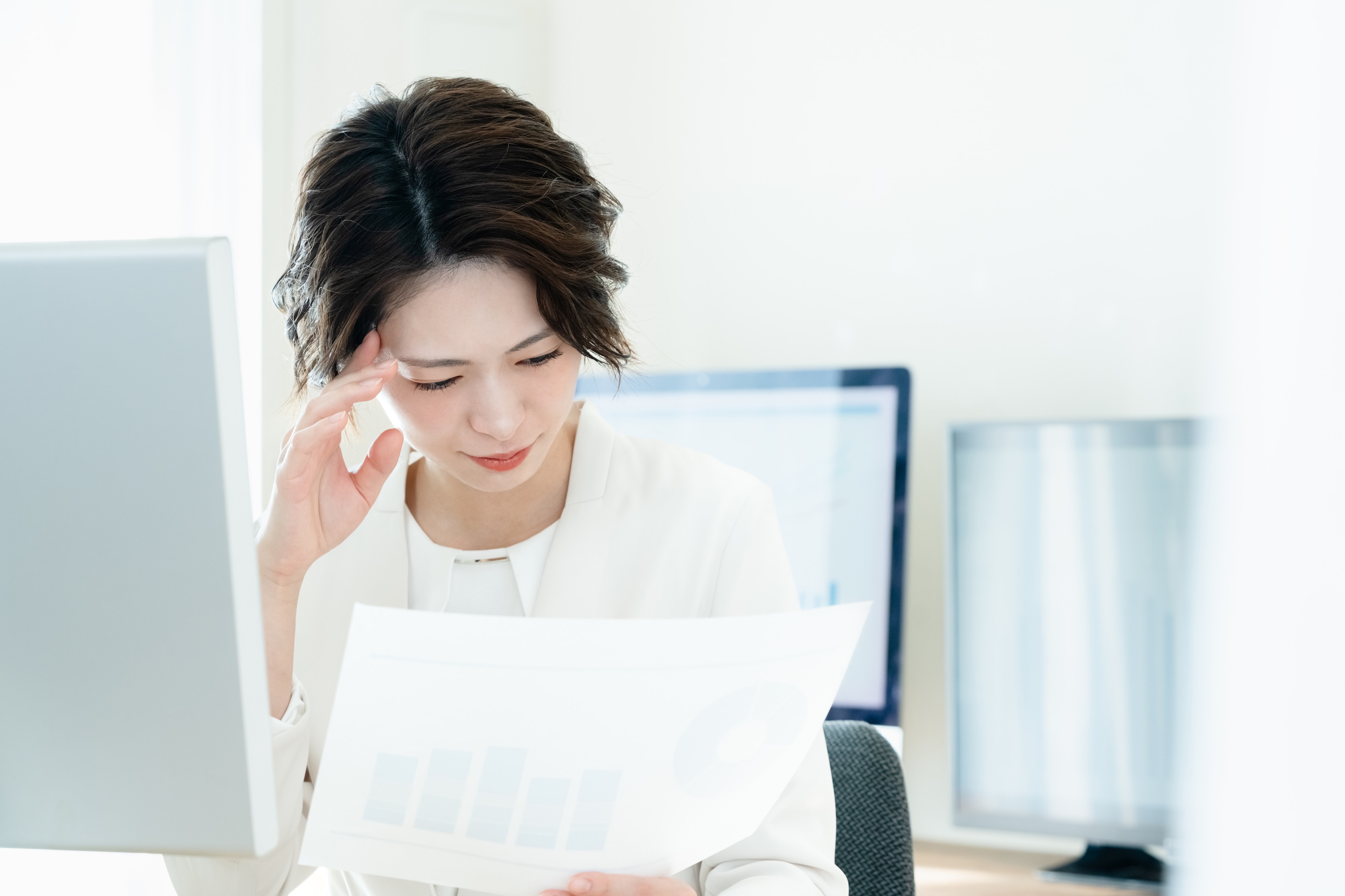
通勤手当は従業員の通勤費用を補助する制度であり、企業が支給する場合は就業規則に定めておくことが法的に求められています。
通勤手当においては、支給条件や金額、通勤手段ごとの取扱いを曖昧にしていると支給基準が属人的になり、トラブルの原因になりかねません。
本記事では、通勤手当を就業規則に記載する際の基本的な考え方から就業規則の記載例、注意すべきポイントまでわかりやすく解説します。
目次[非表示]
就業規則に通勤手当について記載する目的
就業規則は、労働者が常時10人以上いる事業場で作成・届出が義務付けられており、通勤手当を含む賃金に関する事項は「絶対的必要記載事項」として必ず記載しなければなりません。
就業規則には、通勤手当の支給条件や計算方法などを記載することが一般的で、給与計算時には原則として就業規則に沿った方法で計算されます。通勤手当について就業規則に記載されていれば、支給条件や計算方法が明確化され、従業員とのトラブル予防にもつながります。
なお、就業規則とは別に「賃金規程」などの付属規程で管理することも認められており、その場合は就業規則に「別に定める」といった文言を入れる形で規定しても構いません。
参考:兵庫労働局「就業規則」
就業規則に通勤手当を記載しないとどうなる?
賃金に関する事項は、就業規則における「絶対的必要記載事項」とされているため、企業が通勤手当を支給する場合には、その内容を就業規則に定める必要があります(労働基準法第89条)
また、通勤手当の支給条件や計算方法について記載しないと、実務上の運用が属人的になり、想定外のトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
例えば、従業員がテレワークで勤務している期間通勤手当の計算方法を就業規則に定めず、担当者に任せられている運用では、計算ミスが発生する可能性があります。
通勤手当に関する支給条件や金額、支給方法、例外などを就業規則で定めておくことでそうしたトラブル防止につながります。
参考:e-Gov法令検索「労働基準法」
就業規則への記載内容のポイント
通勤手当について就業規則へ記載する際は、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 支給条件
- 通勤手段
- 通勤経路および方法の指定
- 計算方法・支給額
- 中途入社や欠勤等の取り扱い
- 通勤経路変更時の届出
- 在宅勤務時の取り扱い
支給条件
通勤手当を支給する条件を定めておきましょう。
例えば「自宅から勤務地までの距離が2km未満なら通勤手当は支給しない」など、支給条件を設定するのが一般的です。
また「特別な事情のある場合を除き特急料金、有料座席料金は支給対象としない」として特定料金を制限する場合もあります。
通勤手段
主に電車やバスなどの公共交通機関、自動車やバイクの利用の可否など、どのような通勤手段に対して支給するかを定めます。
自動車等のマイカー通勤を認める場合は、ガソリン代や駐車料金などの費用負担の範囲、マイカー通勤が許可される通勤距離についてなど、具体的なルールを定めておくことが望ましいでしょう。
通勤経路および方法の指定
通勤手当の算定基準となる通勤経路は、「最も経済的かつ合理的な経路」に限定する旨を定めるのが一般的です。
就業規則に定めておくことで、従業員が迂回ルートや不必要に高額な経路を申請することを防止できます。
通勤手当における「最も経済的かつ合理的な経路」のチェックポイントについては下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
計算方法・支給額
通勤手当の計算方法や支給額は、労働日数に対して実費を支給するのか、定期代を支給するのか、またマイカー通勤の場合はガソリン代から計算するのかなど、様々な方法が考えられます。
例えば、公共交通機関の定期代を支給する場合は「自宅から会社までの最も経済的かつ合理的な経路による公共交通機関の6ヶ月定期券相当額を支給する」などと記載することが考えられます。
中途入社や欠勤等の取り扱い
通常時の計算方法だけではなく、中途入社や退職時の扱い、欠勤・休職時の計算方法など状況に応じた計算方法を記載しておくとよいでしょう。
ただし、定期代を6ヶ月分などでまとめて支給している場合は、数日の欠勤により支給額を都度変更する運用は実務上煩雑になります。そのため、定期代を支給している場合には「退職や休職時に、精算等の対応を行う」といった運用が一般的です。
一方、1ヶ月単位や実費精算方式を採用している場合には、出勤日数に応じて支給する場合もあります。自社の支給形態に応じて、就業規則または社内の通勤費マニュアル等で方針を定めておくとよいでしょう。
通勤経路変更時の届出
従業員が引越しや経路変更等で通勤手当の支給条件に変更が生じた場合に、申請が必要である旨を定めることで運用がスムーズになります。
例えば、「従業員は通勤経路に変更が生じた場合は、速やかに『通勤手当支給申請書』を会社に提出し、承認を得なければならない」などと記載することで従業員が申請方法を迷わなくなります。
在宅勤務時の取り扱い
在宅勤務(テレワーク)が普及した現在では、出社頻度が少ない従業員への通勤手当の扱いも明確にしておく方が望ましいでしょう。
通勤手当の就業規則記載例
就業規則には、できるだけ詳細に、かつ明確に記載することが大切です。ここでは通勤手当の就業規則の記載例を紹介します。
【記載例 】
(通勤手当) 2.通勤手当は、従業員が申請し、会社が最も経済的かつ合理的であると認めた通勤経路および方法に基づき以下の金額を支給する。 (1)公共交通機関利用者 (2)自動車通勤者 (3) 公共交通機関と自家用車等の併用 3.月の途中で採用または退職した場合、あるいは暦月で1ヶ月を超える長期の休職・休業等により、通勤手当の支給または精算が必要となった場合は、次のとおり取り扱う。 4.従業員は入社時および通勤経路に変更が生じた場合は、速やかに「通勤手当支給申請書」を会社に提出し、承認を得なければならない。 |
通勤手当の就業規則の記載に関するよくある質問
ここでは、通勤手当について就業規則に記載する際によくある質問をQ&A形式でお答えします。
Q1:テレワーク主体の働き方でも通勤手当を支給しなければなりませんか?
必ずしも支給する必要はありません。実費精算や出社日のみの支給など出社日数に応じた支給方法に見直すことも検討しましょう。
ただし、従業員に不利益となる変更を行う場合は労使間での合意や適切な手続きが必要です。
Q2:マイカー通勤を規定する場合に注意点はありますか?
マイカー通勤を認める場合は、距離に応じたガソリン代の支給や定額支給とする方法があります。駐車場代を含めるかどうかも明確にしておくとよいでしょう。
さらに、任意保険加入を義務づける等、安全面への配慮も規定しておくことが望まれます。
Q3:就業規則に記載しても実務で正しく運用されているか不安です
就業規則に沿ったマニュアルを用意するなど適切に運用ができる環境を整えましょう。
また、通勤費管理システムを導入すれば誰でも就業規則に沿った運用が可能になります。通勤費管理システムは、就業規則に沿った計算方法を自動的に行い、さらに転勤や引っ越しによる通勤手当の払戻計算も自動化され、計算ミスも軽減できます。
まとめ
通勤手当は企業にとって継続的に発生する固定的な賃金であり、その取り扱いを就業規則に定めておくことは従業員とのトラブルを防ぐうえで重要です。就業規則に支給条件や計算方法、欠勤等の取り扱いなどを定めておけば、企業と従業員との共通認識が生まれ、運用の安定につながります。
また、働き方の多様化が進み、通常の勤務とテレワークなどが混在する現代では、従来の通勤手当制度では対応しきれない場面も少なくありません。変化に柔軟に対応し続けるには、就業規則の定期的な見直しと、通勤に関する管理業務の効率化が不可欠です。担当者が運賃や経路を手作業で確認し、個別に妥当性を判断する作業には膨大な手間と属人化のリスクが伴っています。
こうした課題を背景に開発されたのが「駅すぱあと 通勤費Web」です。運賃確認、経路の妥当性チェックといった業務を自動化し、人的ミスの削減や業務負担の軽減が可能となります。テレワークなどの多様な勤務形態にも対応できる柔軟性を備えており、通勤手当管理における新しいスタンダードとなるでしょう。
手作業による運賃確認や経路審査、経費精算に限界を感じている方には「駅すぱあと 通勤費Web」の導入をおすすめします。
詳しい資料はこちらからダウンロードいただけます。