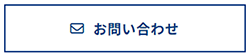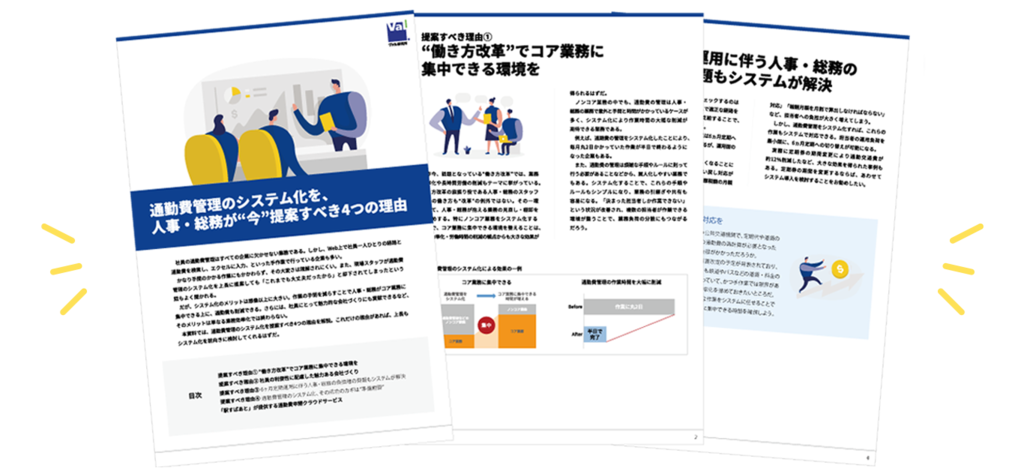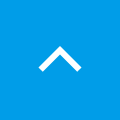オフピーク定期券とは? 導入にあたって企業がすべきこと

JR東日本が2023年3月18日から開始した“オフピーク定期券”を活用すれば、より快適に通勤できるようになります。オフピーク定期券を導入するにあたって、企業はさまざまな準備をする必要がありますが、具体的にはどのようなことを進めればよいのでしょうか。
本記事では、オフピーク定期券の概要と、導入にあたって企業が対応することを解説します。
目次[非表示]
オフピーク定期券とは
オフピーク定期券とは、平日朝のピーク時間帯以外の、オフピーク時間帯のみに利用できる割安な通勤定期券のことです。入場のタイミングでピーク時間帯かどうかが判定され、定期券を利用できる時間帯であれば、お得に乗車できます。利用できる時間帯は限られているものの、その分安く購入できる点が大きな特徴です。
またJR東日本は「オフピーク定期券の普及を通じて、企業の働き方改革を後押しし、ウェルビーイングな社会を目指します」とし、2024年10月1日からオフピーク定期券の価格を値下げしました。これまでも通常の通勤定期券と比べて約10%割安でしたが、価格が改定された現在では、約15%割安になっています。このことから、さらにお得に購入できるようになったことがお分かりいただけるのではないでしょうか。
では、実際に赤羽駅から新宿駅までのオフピーク定期券を6ヶ月分購入する場合を例に、どの程度安くなるのかを見てみたいと思います。
▼赤羽駅から新宿駅までのオフピーク定期券(6ヶ月分)の支給額の変化
通常の通勤定期券の価格 | 改定前のオフピーク定期券の価格 | 改定後のオフピーク定期券の価格 |
33,480円 | 29,870円 | 28,290円 |
価格が改定される前は、6ヶ月分のオフピーク定期券は29,870円でしたが、改定後は28,290円となりました。同区間で通常の通勤定期券を購入する場合は、6ヶ月で33,480円であることから、その差の大きさがうかがえます。
なお、オフピーク定期券はJR東日本が提供しているため、現状ではSuicaでのみ販売されています。通学定期券やグリーン定期券も対象外となることは、押さえておきたいところです。
オフピーク定期券の対象エリア
オフピーク定期券は利用できる時間帯だけではなく、エリアも限定されています。対象となるエリアは、JR東日本が定める電車特定区間内です。
電車特定区間とは東京や大阪など、JRの電車を利用する乗客が多い区間に定められているもので 、ほかのエリアよりも運賃が安いのが特徴です。このエリアにある発着駅の改札を通るのであれば、オフピーク定期券を利用できます。
ただし対象エリアであったとしても、後述するピーク時間帯に入場した場合や、途中経路が適用区間外の場合はオフピーク定期券を利用できません。
オフピーク定期券の利用が向いている従業員
通勤手当の支給額を抑え、経費削減にも一役買ってくれるオフピーク定期券ですが、どのような従業員に適しているのでしょうか。
結論からいうと、出勤するタイミングを自由に決められる方に向いています。
平日朝のピーク時間帯を避けられるのであれば、「オフピーク定期券を購入したけれど利用できずに、IC普通料金がとられた」という事態が起こる心配はありません。そのため、フレックスタイム制度が導入されている企業で働く方や、始業時間が遅い店舗で働く方などは、オフピーク定期券を利用したほうがお得に乗車できるといえます。
ピークとされている時間帯
オフピーク定期券の安さに惹かれて購入したものの、通勤時間がピーク時間帯と被ってしまうのは避けたいところです。平日朝のピークとして定められている時間帯は駅によって異なるため、どの時間帯が該当するのかは事前に押さえておくのが賢明です。
以下に、ピーク時間帯の一例をまとめました。
▼駅によって異なるピーク時間帯
- 大宮駅:6時45分~8時15分
- 赤羽駅:7時05分~8時35分
- 横浜駅:7時00分〜8時30分
- 川崎駅:7時10分~8時40分
前述の通り、ピーク時間帯の判定は、改札への入場時に行われます。遅延の影響でオフピーク時間帯から外れてしまったとしても、特別な措置はありません。この場合はIC普通運賃がかかります。
なお、電車の乗り換えで一度改札を出た後に別の改札を通る場合、再入場する際にも時間帯が判定されます。自宅の最寄駅ではピーク時間帯を外れていても、途中の改札を通る乗換駅でピーク時間帯に該当してしまわないか、注意が必要です。
企業におけるオフピーク定期券を利用する従業員への対応
オフピーク定期券を利用する従業員が増えていくことが予想されるなかで、企業側も事前の準備が必要です。ここからは、企業側が対応すべき3つのポイントを紹介します。
➀適用対象者の有無を確認する
オフピーク定期券は、どの企業の、どの従業員にも利用が適しているわけではありません。平日朝のピーク時間帯を避けなければならない性質上、利用が最適な従業員が限られるためです。
オフピーク定期券の導入に際しては、部署間で連携をとりつつ、従業員の出社時間が変わることで業務に支障をきたさないかどうかをよく検討する必要があります。そして対象となる従業員が誰なのかを、事前に洗い出しておくことも重要です。
②社内の運用ルールを整備する
オフピーク定期券の導入では、社内の運用ルールも見直して、新たなルールを整備するのが一般的です。業務だけでなく、育児や通院などの家庭の事情も想定したうえで、時差通勤のパターンをあらかじめ設けておきます。
また、外回り営業の部署であれば、打ち合わせや業務の都合によってピーク時間帯の通勤が避けられない事案も考えられます。オフピーク定期券を所有していても、別途運賃がかかるケースがある点には要注意です。
そのような場合の精算方法をはじめとして、通勤手当の社内の運用ルールは明確に定めておく必要があります。
③就業規則を変更する
社内の運用ルールを整備した後は、就業規則も変更しなければなりません。
オフピーク定期券の適用を承認する範囲や、オフピーク定期券を持ちながら止む無くピーク時間帯に出勤した場合の対応などを追加します。オフピーク定期券に関連して起こり得る事象を事前に規則として設けておけば、従業員との認識の相違をなくし、トラブルも未然に防げるといえます。
オフピーク定期券が企業に与える影響
オフピーク定期券を導入すると、企業としては通勤費の支給額を抑えることができ、また時差通勤で個々の通勤しやすさが向上するなど、働き方改革の推進につなげることもできます。
企業にとっても、働く従業員にとってもメリットのあるオフピーク定期券ですが、導入により通勤費の精算業務が煩雑になるおそれがあります。通勤費を支給する際に、「この従業員はオフピーク定期券の対象となるのか」を判断しなければならないためです。
また、従業員から正しいルートで申請されているか、あるいは入場の時間帯によって変わる通勤費の金額の確認などに時間がかかるかもしれません。
オフピーク定期券の利用による業務の煩雑化を防ぐためにも、通勤費管理システムの導入は有効な手です。通勤費管理システムでは、通勤経路の登録や通勤費の支給などの、経理業務を一元管理できます。
近年では、オフピーク定期券が利用できる通勤経路なのかを自動で判断したうえで、通勤費の支給額を計算する機能が備わっているものもあります。通勤費管理システムを上手に活用すれば、オフピーク定期券を導入した後も業務を円滑に進められるはずです。
まとめ
この記事では、オフピーク定期券について以下を解説しました。
- オフピーク定期券とは
- ピークとされている時間帯
- 企業におけるオフピーク定期券を利用する従業員への対応
- オフピーク定期券が企業に与える影響
平日朝のピーク時間帯以外に使えるオフピーク定期券は、通常の通勤定期券と比べて割安で購入できる点がメリットです。2024年10月1日に価格が改定され、現在ではさらにお得に購入できるようになりました。オフピーク定期券を導入する場合、企業は対象となる従業員の確認や、運用ルールの整備などに取り組む必要があります。
通勤手当業務の煩雑化を防ぎたいのであれば、通勤費をシステムが自動で管理する『駅すぱあと 通勤費Web』を導入してみてはいかがでしょうか。『駅すぱあと 通勤費Web』では2023年3月より、オフピーク定期券を導入した場合、通勤費の支給額がいくらになるのかを予測できる『オフピーク定期切替シミュレーション』機能の提供を開始しました。
この機能は、オフピーク定期券の導入可否を悩むときの判断材料ともなるため、ぜひご活用ください。
ご興味のある方は、こちらからお問い合わせください。
『駅すぱあと 通勤費Web』の特徴や機能を解説した製品資料は、こちらからダウンロードいただけます。