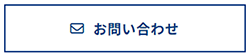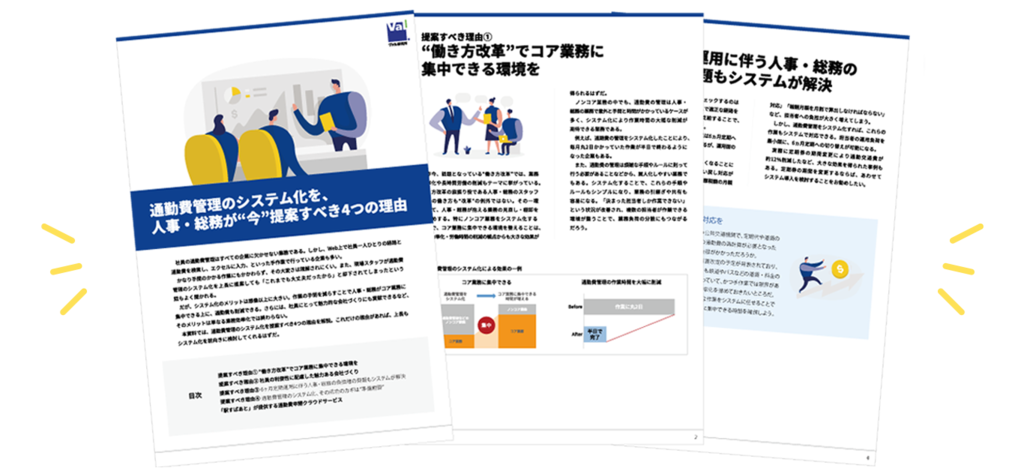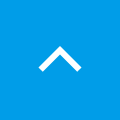通勤手当と旅費交通費の違いは? 社会保険料との関係も解説

企業が従業員に支払う交通費には、“通勤手当”と“旅費交通費”の2種類に分けられます。両者には共通する部分があるものの、社会保険料や所得税の算出に影響することから、明確に区別する必要があります。
本記事では、通勤手当と旅費交通費の概要や、それぞれの違いを解説します。
企業が支払う交通費の種類
企業が支払う交通費と聞いて思い浮かぶのは、通勤手当と旅費交通費ではないでしょうか。
同一経路での定期的な移動に伴い発生する費用が通勤手当、業務で移動する際に不定期で発生する費用が旅費交通費です。ここからは、それぞれの特徴を詳しく解説します。
①通勤手当
通勤手当は通勤費や通勤交通費ともよばれ、その名の通り、従業員が通勤する際にかかる交通費のことを指します。鉄道やバスの運賃のほか、車での通勤に必要なガソリン代も該当します。
通勤手当の支給は、あくまでも福利厚生の一つであり、企業が法的な義務を負っているわけではありません。そのため、費用の一部のみを支給したり、金額に上限を設けていたりと、支給方法は企業によってさまざまです。
②旅費交通費
従業員の営業活動や出張時に要する交通費が、旅費交通費です。出張費や出張旅費と称されるケースもあります。
旅費交通費は、就業規則への記載の有無にかかわらず、支給義務が発生します。
ただし、出張における有料特急やグリーン車などの利用については就業規則にて企業ごとにルールを設けることが可能です。
通勤手当と旅費交通費の違い
通勤手当と旅費交通費には、企業の支給義務の有無以外にも次のような違いが見られます。
▼通勤手当と旅費交通費の違い
通勤手当 | 旅費交通費 | |
企業の支給義務 | なし | あり |
主な支給内容 | 通勤に際してかかった交通費 | 営業活動や出張時にかかった交通費 |
主な支給方法 | 給与に上乗せするかたちで支給 | 領収書をもとに経費精算するかたちで支給 |
多くの場合、通勤手当は決まった通勤経路に基づく金額が、給与に上乗せするかたちで支給されます。一方で、旅費交通費は、時と場合によって異なる経路が利用されるため、同じ行き先でも毎回同じ金額になるわけではありません。企業によって異なりますが、1ヶ月ごとに領収書を提出し、それに基づき現金で支給されるのが一般的です。
なお、通勤手当と旅費交通費は、移動にかかった費用を企業が負担するという点が共通しています。
社会保険料との関係
通勤手当は、社会保険料と密接な関係にあります。
健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料の金額は、企業が年に一度届け出る“算定基礎届”によって、決定されます。この算定基礎届は、従業員の標準報酬月額を見直すための手続きです。
標準報酬月額は、その年の4~6月の3ヶ月間の報酬額をもとに算出され、この報酬額には基本給だけではなく、通勤手当をはじめとする諸手当も含まれます。つまり、通勤手当の額が大きいほど社会保険料が多くなるという仕組みです。
また、標準報酬月額の計算式に、旅費交通費は含まれません。
所得税との関係
続いて、交通費と所得税の関係を見てみます。
従業員が支払う所得税は、給与の合計額から、社会保険料控除や配偶者控除などの各種控除額を差し引いて決定されます。
通勤手当は、原則として給与と見なされるため、所得税の課税対象です。ただし、通勤手当には非課税限度額が定められており、その額を上回らない限りは課税されません。
一方で、旅費交通費は課税対象に含まれない実費弁償です。
▼通勤手当の非課税限度額
区分 | 非課税限度額 | |
①交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) | |
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道2km未満の場合 | 全額課税 |
通勤距離が片道2km以上10km未満の場合 | 4,200円 | |
通勤距離が片道10km以上15km未満の場合 | 7,300円 | |
通勤距離が片道15km以上25km未満の場合 | 13,500円 | |
通勤距離が片道25km以上35km未満の場合 | 19,700円 | |
通勤距離が片道35km以上45km未満の場合 | 25,900円 | |
通勤距離が片道45km以上55km未満の場合 | 32,300円 | |
通勤距離が片道55km以上の場合 | 38,700円 | |
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) | |
④交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度150,000円) | |
参照:国税庁『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』
参照:国税庁『No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当』
まとめ
この記事では、通勤手当と旅費交通費について以下の内容を解説しました。
- 企業が支払う交通費の種類
- 通勤手当と旅費交通費の違い
- 社会保険料との関係
- 所得税との関係
どちらも交通機関の利用に必要な費用ですが、違いを曖昧にしてはいけません。なぜなら、交通費の支給額は社会保険料や所得税を算出する際に影響を及ぼすからです。
『駅すぱあと 通勤費Web』を利用すれば、通勤手当を簡単に計算できます。通勤経路の申請・承認から、経路変更による払戻金額・運賃改定で生じた差額までを自動計算し、管理業務の手間を大幅に減らすことが可能です。
また、旅費交通費の精算には、ブラウザ上で経路検索から申請、承認まで行える『駅すぱあと 旅費交通費精算Web』をご利用ください。
ご興味のある方は、こちらからお問い合わせください。
『駅すぱあと 通勤費Web』の特徴や機能を解説した製品資料は、こちらからダウンロードいただけます。