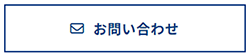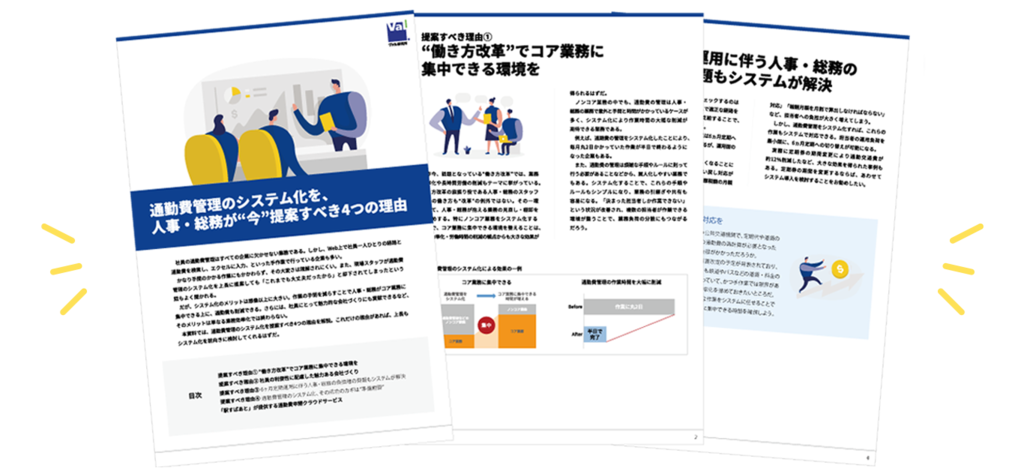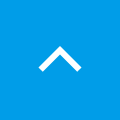労働基準法に通勤手当の規定はある? 支給時のポイントは?

通勤手当を支給するためのルールは、企業によって異なります。支給条件を決めるにあたっては、労働基準法の存在が気になる人事・総務担当者もいるかもしれません。
本記事では、「労働基準法には、通勤手当に関する規定があるのか」という疑問にお答えします。
目次[非表示]
労働基準法における通勤手当の規定の有無
結論からいうと、労働基準法には通勤手当に関する規定は定められていません。
通勤手当はあくまでも福利厚生の一つであり、従業員に必ず支払わなければならないものではないからです。そのため、企業ごとに通勤手当の有無や、支給方法などに違いがみられるわけです。
通勤手当と関係のある労働基準法の条文
通勤手当の支給を義務づける規定はありませんが、労働基準法には通勤手当に関係する条文があります。その一つとして挙げられるのは、“賃金”について定義されている労働基準法第十一条の内容です。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』
上記に則して、就業規則や賃金規定で支給が定められている通勤手当は、すべて賃金として扱われます。支給条件を満たしている従業員に対して、通勤手当を支払わない場合は“賃金未払い”となり、労働基準法に違反するためご注意ください。
通勤手当の規定を考える際のポイント
通勤手当に関するルールは自社で定める必要がありますが、その際のポイントとしてはどのようなものが挙げられるのでしょうか。
①支給条件を明確にする
まずは通勤距離や出勤日数などを基に、通勤手当の支給条件を具体的に考えることが重要です。条件が曖昧だと、のちになんらかのトラブルが起こるかもしれません。このようなリスクを防ぐためにも、通勤手当の支給条件は明確にしておくのがベターです。
また、支給条件を考える際には“通勤手段”も考慮する必要があります。特に、車やバイクでの通勤を認める場合は、条件の決め方に注意したいところです。
車種によって燃費が異なるため、従業員と企業の双方が納得できる方法で支給額を決定することが大切です。日々変化するガソリン代の計算に手間をかけたくないときは、燃費ではなく通勤距離で支給額の条件を決めることをおすすめします。
②通勤手当の非課税限度額を確かめる
通勤手段によって異なりますが、通勤手当には非課税限度額が定められています。この限度額を超えると給与所得の対象となり、課税される点はあらかじめ押さえておきたいところです。
例えば、通勤時に公共交通機関を利用する場合、非課税限度額は1ヶ月15万円となります。電車やバスで通勤する従業員には、通勤手当として定期代を支給するのが一般的です。
また車や自転車を利用する場合、通勤手当の非課税限度額は“通勤距離”に応じて変動し、以下のように決められています。
▼車や自転車で通勤する場合の非課税限度額
片道の通勤距離 | 1ヶ月あたりの非課税限度額 |
2km未満 | 全額課税対象 |
2km〜10km未満 | 4,200円 |
10km〜15km未満 | 7,300円 |
15km〜25km未満 | 13,500円 |
25km〜35km未満 | 19,700円 |
35km〜45km未満 | 25,900円 |
45km〜55km未満 | 32,300円 |
55km以上 | 38,700円 |
自宅から職場までが近い従業員に対しては、車や自転車の利用を認めることがあるかもしれません。しかし、通勤距離が2km未満のケースでは、支給する通勤手当が全額課税されてしまいます。反対に通勤距離が長すぎる場合も、限度額を超えてしまう可能性があります。そうならないためにも通勤距離を確認したうえで、支給条件をご検討ください。
出典:国税庁『マイカー・自転車通勤者の通勤手当』
通勤手当を支給するときに気をつけたいこと
最後に、通勤手当を支給するにあたって覚えておきたいことをお伝えします。
まず挙げられるのは、通勤手当に関する労働基準法の条文を確認し、違反となる行為をきちんと理解することです。通勤手当は“労働の対償”として支給されるものであり、賃金の一部として扱われます。そのため、自社で“通勤手当を支給する”と定めている場合は、支給漏れが発生しないようご注意ください。
また、通勤手当の不正受給や手作業によるミス、申請の確認漏れなどを防ぐためにも、通勤費管理システムの活用をおすすめします。通勤費管理システムを導入すれば、支給額の自動計算はもちろん、通勤手当に関する従業員の情報もまとめて管理できます。
トラブルを未然に防げるだけではなく、煩雑な通勤費管理業務も効率的に進められるようになるはずです。“最も経済的かつ合理的な経路”を容易に検索できることも、通勤費管理システムならではの利点です。
最も経済的かつ合理的な経路について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
まとめ
この記事では、労働基準法と通勤手当の関係について、以下の内容をお伝えしました。
- 労働基準法における通勤手当の規定の有無
- 通勤手当と関係のある労働基準法の条文
- 通勤手当の規定を考える際のポイント
- 通勤手当を支給するときに気をつけたいこと
通勤手当は企業が定める福利厚生の一部であり、労働基準法には規定が定められていません。ただし労働基準法第十一条のように、通勤手当に関する条文もあります。気づかないうちに労働基準法に違反してしまわないよう、内容は事前にご確認ください。
通勤手当の支給に際しては、不正受給をはじめとするトラブルを防ぐためにも『駅すぱあと 通勤費Web』を利用してみてはいかがでしょうか。自動化によって、通勤費管理業務を効率的に進められるようになり、人事・総務担当者の負担を減らすことができます。
ご興味のある方は、こちらからお問い合わせください。
資料はこちらからダウンロードいただけます。