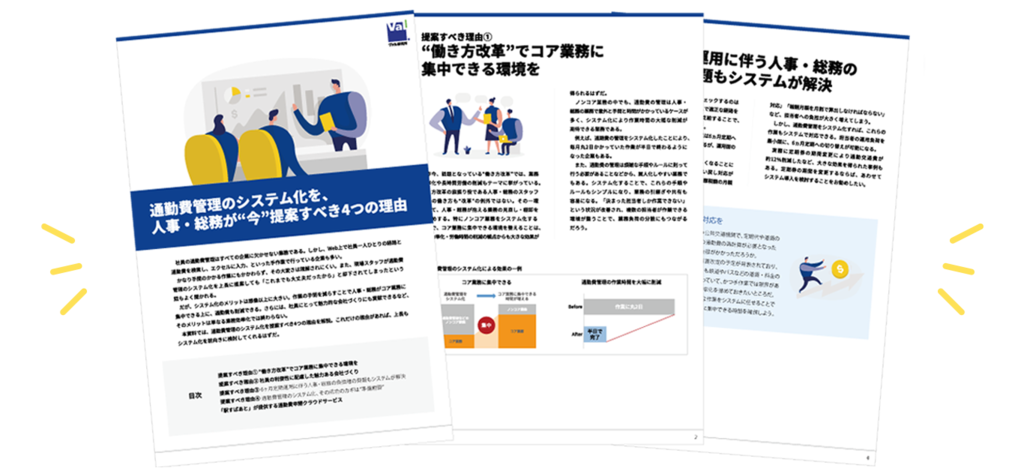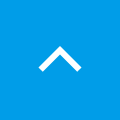通勤中のケガは労災になる?判断基準と実務対応をわかりやすく解説

従業員が通勤途中の事故でケガをした場合は、原則として労災保険が適用されます。しかし「通勤中であればすべて労災保険の対象になる」というわけではなく、法令で定められた条件を満たすかどうかで判断されます。
企業の担当者にとって、通勤の範囲や労災保険の申請方法を正しく理解しておくことは、従業員の安心と企業の信頼性を守るうえで欠かせません。
本記事では、通勤災害の基本的な考え方や判断基準、具体的な事例をわかりやすく解説します。
目次[非表示]
通勤中の労災の基本的な考え方
通勤中のケガが労災と認められるかどうかは、まずその移動が法律上「通勤」にあたるかを判断することから始まります。
一見すると日常的な出勤・退勤の移動も、経路や目的によっては通勤とは扱われない場合があります。特に「移動の定義」や「逸脱・中断」といった概念、そして労災保険の対象者の範囲を理解しておくことが大切です。ここでは、通勤災害の判断の土台となる基本的な考え方を整理します。
参考:厚生労働省「通勤災害について」
移動の定義
通勤中の労災における「通勤」とは、単に職場への行き帰りを指すだけではありません。法律上は、以下のように定義されています。
【法律上の通勤の定義】
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動(単身赴任・二拠点生活など)
なお、通勤の途中で通勤とは関係のない用事を挟んだり、道を外れたり(逸脱または中断)すると原則としてその間と再開後の移動は通勤とはみなされません。
つまり労災になるかどうかは、その移動が法律上「通勤」に当たるかどうかが最初の判断ポイントとなります。
逸脱または中断とは
原則として通勤中に行った「逸脱」または「中断」の行為は、その間と再開後の移動は通勤とはみなされません。
「逸脱」とは、通勤途中に通勤目的と関係のない理由で経路を外れることを指します。例えば、帰宅途中に経路から離れた場所の飲食店に寄るケースなどです。
また「中断」とは、経路上で通勤と関係のない行為を行うことを意味します。例えば、会社帰りに映画館に寄って映画を鑑賞している時間などです。
ただし、以下のような最小限度の行為である場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤と認められます。
- 日用品の購入
- 職業能力向上のための教育訓練
- 選挙権の行使
- 病院での診察・治療
- 継続的な家族介護
これらは日常生活上必要な行為とされ、行為後の移動は通勤として認められます。
労災保険の対象者
労災保険の対象者は原則労働者として雇用されているすべての人です。たとえば、週1日のみ勤務している場合でも労災保険は適用されます。
ただし、代表取締役(社長)や監査役などの役員は兼務役員の場合を除き労働者ではないため、対象外となります。なお、中小企業の役員の場合は、労災保険の特別加入をすることで労災保険が適用されます。
参考:厚生労働省「労災保険の適用者について」
通勤中の労災の判断基準
通勤中の労災にあたるかどうかは、移動の経路や方法が「合理的」であったかがポイントになります。合理的とは、単に本人が便利と感じる経路や手段という意味ではなく、一般的に見て通勤目的に沿っていることを指します。
ここでは、通勤災害の判断で必ず押さえておきたい「合理的な経路」と「合理的な方法」について解説します。
合理的な経路
「合理的な経路」とは、従業員が通常利用している経路です。道筋が複数存在しても一般的に利用する経路であれば合理的な経路に該当します。また、事故や運休などでやむなく迂回した場合の経路も状況に照らして合理的と評価される余地があります。
一方で、特段の事情のない大回りや、通勤目的と結び付けにくい寄り道が長く続くような経路は、合理的な経路とは言いにくいでしょう。
合理的な経路については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
合理的な方法
合理的な方法とは、電車やバスなどの公共交通機関、自動車・自転車・徒歩といった通勤方法のことです。一般的な手段であれば、普段利用しているかどうかにかかわらず合理的とみなされやすい傾向にあります。
一方で、健康増進や趣味といった通勤以外の目的が前面に出る手段への切り替えは、合理性が否定される可能性があります。
通勤中の労災と認められる事例と認められない事例
通勤中の労災は、要件に該当していない場合には労災として取り扱われない可能性があります。ここでは通勤中に起こった事故で、労災と認められる事例と認められない事例を紹介します。
なお、労災に該当するかの最終的な判断は労働基準監督署で行われます。同様の事例でも状況によっては異なりますのであくまで参考としてご覧ください。
通勤中の労災と認められる事例
例1: 通常は電車通勤だが大幅な遅延が発生。やむなく自転車で出社を試みるが途中に転倒してケガをした。
→ 当日の交通事情から方法変更に相応の理由があり、全体として合理的な経路・方法の範囲にとどまることから、通勤災害として扱われる可能性があります。
例2: 電車の運休で通常とは別の路線や駅を経由して出勤したところ、階段で転倒。
→ 運休や混雑回避などの実情があって迂回したのであれば、別経路であっても「合理的な経路」に含まれる余地があるため、労災として認められる可能性があります。
例3: 自然災害で避難所に一時的に居住。翌日に避難所から勤務先へ向かう途中で転倒。
→ 災害時は避難場所が一時的な住居場所とされるため、避難場所の移動が通勤に該当する可能性があります。
自転車の通勤については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
通勤中の労災と認められない事例
例1: ダイエット目的で、通常は電車だが徒歩で通勤し転倒。
→ 手段の選択に通勤以外の目的が強く影響していると評価されると、合理的な方法での通勤と認められにくくなります。
例2: 帰宅途中に同僚と居酒屋へ入店し、退店後の帰路で転倒。
→ 居酒屋への立ち寄りは、例外として認められる日常生活上の最小限の行為には通常あたりません。入店の時点で通勤が中断し、その後の移動は通勤とは扱われない可能性が高いといえます。
例3: 出張のため新幹線駅へ向かう途中で不慮の事故によりケガ。
→ 出張に伴う移動は、「業務中」として認められやすく、通勤中の労災ではなく業務中の労災として保険給付が適用されます。
出張などの旅費交通費については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
通勤中の労災が発生したときの実務対応
通勤中の労災が発生した場合は、まずは事実関係の把握から始めましょう。
発生日時や場所、通常の通勤経路、当日の実際の経路、目的や寄り道の有無、交通障害の状況、ケガの部位・程度などを従業員の申告をもとに確認します。また、裏付け資料などがあれば労災保険の申請書作成がスムーズにできます。
そのうえで、療養の費用負担を従業員に生じさせないため、健康保険ではなく労災保険での受診を案内し、会社欄の証明を記載した所定の書類(例:様式第16号の3 療養の給付請求等)を準備します。
書類が作成できたら、病院や所轄の労働基準監督署に提出しましょう。休業が続く場合には、医師の証明欄が入った休業(補償)給付の申請準備も並行して進めます。
なお、労災保険の手続きについては就業規則等の規定に記載する義務はありません。ただし、事故時の社内報告ルートや担当部署を別紙マニュアル化しておくとより運用がスムーズになります。
就業規則については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
まとめ:通勤中の労災の対応は通勤経路の適切な管理が大切
通勤中の労災は「通勤途中の事故かどうか」だけで決まるものではなく、通勤中の移動か、合理的な経路・方法かという観点から判断されます。そのため実務上では、通勤経路を適切に管理しておくことが大切になります。
「駅すぱあと 通勤費Web」を活用すれば、最も経済的かつ合理的な通勤経路の算出、変更履歴の可視化、申請内容の妥当性の確認など一元的に進めやすくなります。結果として、従業員の安全・安心な通勤を支援しつつ、担当者の事務負担を抑えることが可能です。ぜひ、「駅すぱあと 通勤費Web」のご利用をご検討ください。
詳しい資料はこちらからダウンロードいただけます。