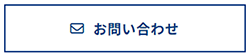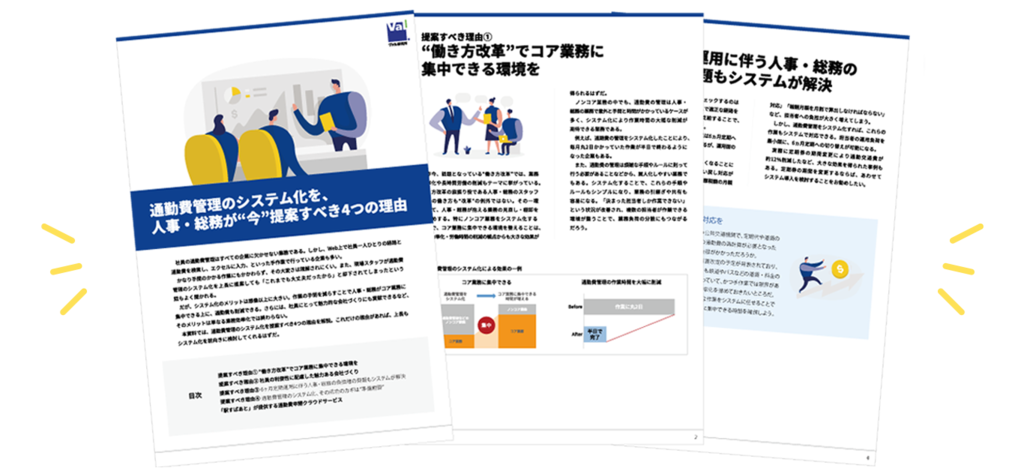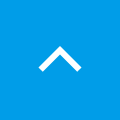通勤手当の課税ルールや非課税限度額を注意点とともに解説

通勤手当について調べているものの、通勤手当の金額が決まる仕組みがよくわからず、お困りの方もいるのではないでしょうか。交通手段によって課税ルールと非課税限度額は異なるため、間違えないように注意しなければなりません。
本記事では、通勤手当の課税ルールと非課税限度額を、注意点とともに解説します。
目次[非表示]
通勤手当とは
通勤手当とは、企業が従業員に支給する、通勤に関する手当のことです。企業によっては、通勤交通費ともよばれます。
通勤に際してかかった費用が支給対象となり、電車やバスなどの公共交通機関の運賃をはじめ、車やバイクで通勤する際にかかるガソリン代も該当します。従業員ごとに通勤手当の額を算出し、給与に上乗せするかたちで支給するのが一般的です。
通勤手当の有無や支給方法などのルールは、企業の就業規則にある給与規程によって決定します。実費支給としているところもあれば、1ヶ月の定期券代を上限としているところもあるように、支給する金額は、企業ごとに独自で設定することが可能です。
なお、厚生労働省の『同一労働同一賃金ガイドライン』では、正規雇用と非正規雇用のあいだに、賃金や待遇の格差があってはならないとされています。通勤手当に関しても以下のように明記されており、企業はこれを遵守する必要があります。
短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければならない。
引用元:厚生労働省『同一労働同一賃金ガイドライン』
そのため、通勤手当の支給ルールを定めた規則は、パートやアルバイトに対しても同じ条件で適用されるものでなければなりません。
交通費との違い
通勤手当も移動に伴う費用ではありますが、ここでいう“交通費”は、従業員が営業活動や出張時に要する費用を指します。支給ルールは、給与規程に従って決定します。
▼通勤手当と交通費の違い
通勤手当 | 交通費 | |
企業の支給義務 | なし | あり |
主な支給内容 | 通勤に際してかかった費用 | 営業活動や出張時にかかった費用 |
主な支給方法 | 給与に上乗せするかたちで支給 | 従業員が立て替えたのちに経費精算 |
課税金額 | 通勤手段によって定められている非課税限度額を超えた額 | 全額非課税 |
非課税限度額が定められている通勤手当とは異なり、交通費は全額非課税です。そのため、所得税を算出する値に交通費が含まれることはありません。
また、両者は支給方法にも違いがあり、通勤手当が給与に上乗せするかたちで支給するのに対し、交通費は従業員が立て替えたのちに経費精算するケースがほとんどです。
労働基準法上は義務ではない
通勤手当は、労働基準法で支給が義務づけられているわけではありません。
企業が費用を負担する福利厚生は、法律で定められている法定福利厚生と、法律で定められていない法定外福利厚生に分けられます。法定福利厚生には、健康保険や厚生年金保険などが、法定外福利厚生には、通勤手当や住宅手当などが該当します。
厚生労働省の『令和2年就労条件総合調査』によると、“通勤手当など”を支給している企業は6,400社のうち、92.3%です。しかし、通勤手当の制度がある企業でも、費用の一部のみを支給したり、金額に上限を設けていたりと、支給方法はさまざまです。
従業員とのトラブルを避けるためにも、支給対象者や支給基準などは就業規則に明記しておく必要があります。
通勤手当の課税ルールと非課税限度額
それでは、本題の通勤手当の課税ルール・非課税限度額について、通勤方法別に解説していきます。
公共交通機関で通勤する場合の非課税限度額
電車やバスなどの公共交通機関を使う従業員への通勤手当は、月に15万円以下であれば非課税対象になります。
ただし、“経済的かつ合理的な経路にかかった費用のみに適用される”という条件が国税庁によって定められています。仮にグリーン車を使ったり、遠回りでも高い運賃になるように申請していたりすると課税対象となるため、申請内容はよく確認しなければなりません。
車・バイク・自転車で通勤する場合の非課税限度額
車やバイク、自転車などで通勤する従業員への通勤手当は、通勤距離に応じて非課税上限額が異なります。
公共交通機関と同様に、車やバイクの場合も合理的なルートであることが非課税対象となる条件です。
詳細な非課税限度額はこちらの記事で詳しく紹介しています。
公共交通機関と、車・バイク・自転車を併用する場合の非課税限度額
公共交通機関とそのほかの交通手段を併用する場合は、以下の1と2を合計した金額が非課税限度額であり、なおかつ1ヶ月あたり15万円までが限度額となります。
▼公共交通機関とそのほかの交通手段を併用する場合の非課税限度額
- 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1ヶ月間の通勤費
- 車・バイク・自転車などを使って通勤する片道の1ヶ月あたりの非課税となる限度額
1ヶ月あたりの非課税限度額を超えている場合は、超過分の金額が給与として課税されます。
通勤手当が課税されるケース
前述の通り、通勤手当は非課税限度額を上回らない限り、所得税がかかりません。ただし、自動車や自転車などの交通用具を使用しており、通勤距離が片道2km未満である場合、支給される全額が課税対象になります。
また、非課税だと思っていた通勤手当が原因で、年収が課税ラインを超えてしまうケースもあります。通勤手当の扱いによって扶養者の控除額に影響が出る場合があるため、注意が必要です。通勤手当の支給額は、非課税限度額を踏まえて考えることが大切です。
在宅勤務の従業員に通勤費の支給は必要?
在宅勤務制度を導入する企業が増えている昨今、制度を利用する従業員に対し“通勤費を支給すべきかどうか”は、担当者にとって気になる論点です。先述の通り、通勤手当は法律で支給が義務づけられているわけではなく、支給の有無や金額は企業の就業規則に基づいて決定します。そのため、在宅勤務の従業員への通勤手当の支給についても、企業ごとに判断が委ねられています。
一般的に、完全な在宅勤務で、勤務地が“自宅”と見なされる場合には、通勤手当の支給に合理性はありません。仮に支給されたとしても、通常の給与と同じく課税対象となります。一方で、基本的には在宅勤務でありつつ、業務上の必要性から時折出社するようなケースでは、実際に出社した日数分に応じた通勤手当を実費で支給する方法が広く採用されています。
ただし、従来の支給方法から実費支給に切り替えるためには、事前に就業規則へ明記したうえで、従業員への説明も必要です。また、勤務地が“自宅”の場合は、出社を出張と見なして交通費を精算するケースもありますが、この場合は、雇用契約や出張旅費規定などとの整合性が求められます。
いずれにせよ、在宅勤務制度の導入に伴い通勤手当の取り扱いを見直す際には、法的なリスクの回避や従業員の理解を得るための丁寧な対応が欠かせません。
在宅勤務における通勤費の扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
通勤手当の課税・非課税における注意点
続いて、通勤手当の課税・非課税ルールにおいて注意したい点を紹介します。
①通勤手当における課税と非課税を間違えないようにする
企業は課税と非課税の対象となる通勤手当を、取り間違えないように要注意です。もし何らかの事情で課税すべき通勤手当を非課税で計上すると、所得税の未納が発生してしまいます。
税金を滞納すると本来納めるべき税金のほかに、延滞金が加算されるおそれがあるため、誤りがわかった時点で会社専任の税理士か税務署に確認し、適切に処理を行う必要があります。
②正社員とパート・アルバイトで待遇差をつけない
非正規雇用という理由だけで、不合理な待遇差をつけたり、差別的な取り扱いを行ったりしてはなりません。これは、2020年4月に施行されたパートタイム・有期雇用労働法でも定められています。
ただし、正社員とパート・アルバイトで出社日数の多少により通勤手当に差が出る分には、問題ありません。
参照元:厚生労働省『パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために』
③不正受給の可能性に留意する
通勤手当は従業員の申請をもとに支給されるので、住所を偽る、あるいは規定外の経路で通勤するなどの方法で、不正受給が発生してしまう可能性もなくはありません。支給基準を明確に定め、従業員一人ひとりの申請内容を精査するなどの対策が不可欠です。
④課税通勤手当を支給したときは年末調整で給与に含める
先述の通り、通勤手当は、通勤手段によって一定額までは非課税となります。ただし、非課税限度額を超えて支給したぶんの金額は課税対象となり、年末調整で給与に含めて計算します。
たとえば、公共交通機関を使って通勤する場合、非課税限度額は最高で1ヶ月あたり15万円です 。仮に16万円を支給したのであれば、課税対象となるのは、差額の1万円です。
⑤社会保険料の計算には通勤手当の全額が含まれる
通勤手当には所得税の非課税枠が設けられており、一定額までは課税対象から除外されます。しかし、社会保険料を算出する際は、通勤手当も計算の対象となり、税制上の取り扱いとは異なります。通勤が生活に必要な行為であることから、社会保険制度上では生活の基盤を支える手当と位置づけられているのです。
たとえば、基本給が月額30万円の従業員が、毎月3万円の通勤手当を受け取っている場合、これらを合計した33万円を基準に社会保険料が算出されます。社会保険料が変動するということは、当然ながら手取り額にも差が生じます。
このように、社会保険料の対象となる金額は、所得税の課税対象額とは一致しない点に注意が必要です。通勤手当が非課税であるからといって、社会保険料の負担も軽くなるわけではないため、企業側と従業員側の双方がこの違いを理解しておかなければなりません。
なお、出張時の交通費や一時的に支給される手当は実費として扱われるため、社会保険料の計算の対象外です。定期的に支給される通勤手当とは性質が異なるため、混同しないよう注意してください。
通勤手当の支給ルールを決めておくとよい項目
通勤手当の支給ルールは、事前に明確に定めて、就業規則に記載しておく必要があります。支給ルールが曖昧な状態では、従業員とのあいだにトラブルを招きかねません。
ここでは、通勤手当の支給ルールで、最低限決めておくとよい3つの項目を紹介します。
支給条件
まず、最低限明確にしなければならないのは、支給対象者です。通勤手段や通勤距離について、支給対象となる条件を定めます。
支給されるのは公共交通機関を利用する場合のみなのか、車や自転車で通勤する場合も該当するのかなど、通勤手段ごとにルールを考えなければなりません。“自宅から勤務地までの距離が片道2km以上となる者”のように、移動距離に関する規則を定めるケースもあります。
通勤経路の決め方
従業員が通勤経路を決める方法も、事前に定めておきます。
たとえば、通勤手段が電車やバスの場合は、自宅の最寄り駅から勤務地の最寄り駅までの最短経路、というふうに決めておくイメージです。車の場合は、距離やガソリン代の算出方法まで決めておくと、トラブルを未然に防げるはずです。
計算方法や上限額
通勤手当の計算方法や上限額に関するルールも、忘れてはならない項目です。電車やバスの定期券を購入する場合は、何ヶ月ぶんの金額を支給するのか、ガソリン代の金額はいつを基準とするのか”など、詳細な規程を定める必要があります。
支給金額に上限を設ける場合は、“通勤手当の支給上限は月額5万円とする”のようなかたちで、就業規則にわかりやすく明記してください。
まとめ
この記事では、通勤手当について以下の内容を解説しました。
- 通勤手当とは
- 交通費との違い
- 労働基準法上は義務ではない
- 通勤手当の課税ルールと非課税限度額
- 通勤手当が課税されるケース
- 在宅勤務の従業員に通勤費の支給は必要?
- 通勤手当の課税・非課税における注意点
- 通勤手当の支給ルールを決めておくとよい項目
通勤手当は基本的に非課税対象ですが、限度額が決められています。公共交通機関を使う場合は月15万円以下、車やバイクなどを使う場合は距離によって異なるなど、従業員の通勤方法により限度額が変わってきます。
通勤手当の計算を行う際は、本来、課税対象であるところを非課税対象としないように注意してください。また、パート・アルバイトであっても待遇差をつけないようにする、不正受給の防止策をとるなどの注意点にも留意することが求められます。
「毎月の通勤手当の計算に時間がかかりすぎる」「計算ソフトを導入したいけれど初めてで不安」といったお悩みをお持ちの方には、通勤手当の自動計算が可能な『駅すぱあと 通勤費Web』がおすすめです。
乗換案内サービス『駅すぱあと』が開発したクラウドサービスで、申請可能な経路の規定を設定して不正を防止したり、非課税限度額を超えていないかを自動チェックしたりすることが可能です。
ご興味のある方は、こちらからお問い合わせください。
『駅すぱあと 通勤費Web』の特徴や機能を解説した製品資料は、こちらからダウンロードいただけます。