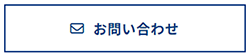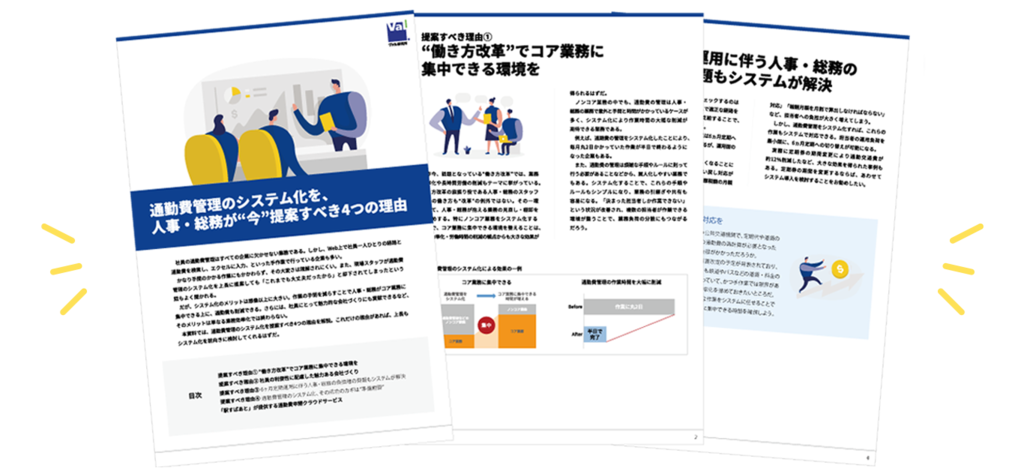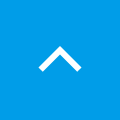"年収の壁"で異なる!通勤手当の年収計算上の扱い方を解説

通勤手当は、いわゆる“年収の壁”によって社会保険や税金の取り扱いに影響をもたらす場合があります。交通手段や費用ごとに適用される規定が細かく定められているため、人事・総務担当者はこれらを正しく理解し、通勤手当を適切に管理することが必要です。
本記事では、年収の壁で変わる通勤手当の扱い方を、注意点とともに解説します。
目次[非表示]
扶養の種類
本題に入る前に、まずは年収の壁を理解するうえで重要な、扶養の種類をお伝えします。扶養は、“税法上の扶養”と“社会保険上の扶養”の2種類に分けられます。
①税法上の扶養
税法上の扶養とは、生計を共にする家族の収入が一定額以下である場合に、納税者の所得から一定の控除を受けられる制度です。従来は扶養対象となる家族の年収が103万円以下であることが条件でしたが、令和7年(2025年)の税制改正により、年収基準が123万円以下へと引き上げられました。
家族を税法上の扶養(被扶養者)とすることで、自身(扶養者)の課税所得が減るため、最終的に納める所得税や住民税が少なくなります。
なお、税法上の扶養の基準は一律に同じというわけではなく、配偶者であるかどうか、または年齢によって異なります。詳しくは後述の年収の壁の解説をご覧ください。
②社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、家計を支える扶養者が加入する社会保険(健康保険)に家族が被扶養者として加入できる制度です。被扶養者は、扶養者と同じ社会保険に加入するため、自身で国民健康保険に加入して個別に保険料を支払う必要がなくなります。
また年金は、配偶者のみが被扶養者(国民年金第3号被保険者)として扶養に加入でき、国民年金保険料を支払う必要がなくなります。
なお、社会保険の扶養に入るためには、被扶養者自身が他の会社の社会保険に加入していないことが条件となります。もし勤務先で一定の労働時間や収入があり、自ら社会保険に加入する要件を満たしている場合は、扶養には入れず、自分で保険料を負担する必要があります。
通勤手当が年収に含まれるかどうかは年収の壁によって異なる
ここからは、年収の壁ごとに異なる通勤手当の扱い方について解説します。
①123万円の壁
123万円の壁とは、税法上の扶養に入れるかどうかを分けるボーダーラインのことです。
前述のとおり、従来は税法上の扶養の要件は年収103万円以下でしたが、改正後は収入が123万円以下であれば扶養の要件に該当します。
通勤手当は税法上の所得と見なされないため、原則として年収に含みません。
ただし、通勤手当が非課税限度額を超過した場合は、その分を年収に含みます。非課税限度額は、非課税となる通勤手当の限度額のことで、交通手段や通勤距離に応じて異なります。詳細は後述するため、引き続きご覧ください。
②160万円の壁
160万円の壁とは、本人の所得税が非課税となるボーダーラインのことです。
令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が65万円に改定され、給与収入が200万円以下であれば95万円の基礎控除が受けられるようになりました。そのため、所得税の非課税枠が年収103万円から最大で160万円まで引き上げられたため、160万円の壁といわれています。
なお、123万円の壁と同様、通勤手当は税法上の所得とみなされませんが、非課税限度額を超過した場合はその分を年収に含めます。
③106万円の壁
106万円の壁とは、社会保険への加入が必要となる目安のことです。自身で社会保険に加入すると配偶者などの社会保険の扶養には入れなくなるため、106万円の壁といわれています。
現在では、以下の条件を満たした場合に勤務先の社会保険への加入義務が発生します。
- 企業規模が従業員51人以上
- 賃金の月額が8.8万円以上(年収106万円以上)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超える見込みがある
- 学生ではない
注意しておきたいのは、106万円の壁の条件である「賃金」には通勤手当は含まれません。次の130万円の壁とは異なるので注意しましょう。
なお、企業規模の要件は2027年10月から段階的に縮小が予定されています。
参考:厚生労働省「年金制度改正の全体像」
④130万円の壁
130万円の壁は、社会保険上の扶養から外れる年収のボーダーラインです。年収が130万円を超える場合、配偶者や親の扶養から外れて自分で社会保険(国民健康保険)への加入が必要です。この「130万の壁」では通勤手当の金額を含んで判断します。
「130万の壁」に通勤手当が含まれる理由は、社会保険料が標準報酬月額(社会保険料を決めるためのみなし月収)を基に算出されているためです。
標準報酬月額を算出する賃金には、通勤手当のほか時間外手当や各種手当も含まれるため、通勤手当を含めて年収が130万円を超えるかの判断をする必要があります。
社会保険料の計算については、以下の記事をご確認ください。
⑤150万円の壁
150万円の壁とは、大学生の年代の家族が社会保険の扶養に入れるボーダーラインのことです。2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の家族(配偶者を除く)の健康保険の被扶養者になれる年収が「130万円未満」から「150万円未満」に拡大されたため、150万円の壁といわれています。
そのため、19歳以上23歳未満の子や兄弟姉妹等を扶養に入れる基準は通勤手当を含めて「150万円未満」となります。
従来は社会保険の扶養に入れることができなかった家族も、条件を満たせば扶養対象にできる可能性が広がったことになります。
150万円の壁は130万円の壁と同様、通勤手当を含んで年収基準を判断します。
そのほか事務手続き上の注意点を補足
通勤手当に関する事務手続き上の注意点を、以下で解説します。
①公共交通機関を利用する場合
先述したように、通勤手当には非課税限度額が設けられており、超過分に対して所得税が課されます。
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、支給される通勤手当が15万円以内であれば非課税となり、15万円を超える場合はその超過分が課税対象となります。
②自家用車を使用する場合
車やバイクといった自家用車で通勤する場合の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて、以下のように定められています。
▼自家用車の通勤手当に適用される非課税限度額
片道の通勤距離 | 1ヶ月あたりの限度額 |
2km未満 | 全額課税 |
2km以上10km未満 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 7,300円 |
15km以上25km未満 | 13,500円 |
25km以上35km未満 | 19,700円 |
35km以上45km未満 | 25,900円 |
45km以上55km未満 | 32,300円 |
55km以上 | 38,700円 |
参照元:国税庁『No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当』
通勤距離が2km以内の場合、徒歩や自転車による通勤が可能と見なされるため、支払われた通勤手当はすべて年収に含まれ、課税対象となります。
③公共交通機関と自家用車を併用する場合
複数の交通手段を併用する場合の通勤手当は、公共交通機関の月額と、自家用車での通勤に適用される非課税限度額との合計が15万円以下である場合に限り、非課税となります。
例えば、自宅から最寄り駅までの11km(支給額は非課税限度額と同額の7,100円)を自家用車で、最寄り駅から勤務先までを電車(1ヶ月あたり1万円)で移動する場合は、月額の合計が17,100円となるため非課税です。この合計額が15万円を超える場合は、超過分が課税対象となります。
なお、使用する通勤ルートが合理的であると認められなければ、課税対象となる場合があるので注意が必要です。
通勤手当の課税ルールの詳細は、こちらの記事で解説しています。
まとめ
この記事では、年収の壁に基づく通勤手当の扱い方について以下の内容を解説しました。
- 扶養の種類には税法上の扶養と社会保険上の扶養がある
- 通勤手当の扱いは年収の壁によって異なる
- 通勤手当には非課税限度額がある
通勤手当を年収と捉えるかどうかは、年収の壁ごとに異なります。税法上の扶養範囲を示す123万円の壁と160万円の壁、社会保険上の扶養範囲を示す106万円の壁では、通勤手当は年収に含みません。対して社会保険への加入が義務化される130万円の壁や150万円の壁では、通勤手当を年収に含めます。
通勤手当は交通手段や費用によっては、課税対象となるケースがあります。人事・総務担当者の方は、通勤手当を管理する際、今回紹介した年収で異なる通勤手当の扱い方や非課税限度額を参考にしてください。
通勤手当の管理でお悩みの方には、通勤手当を自動計算できる『駅すぱあと 通勤費Web』がおすすめです。
乗換案内サービス『駅すぱあと』が開発したクラウドサービスで、既存の給与計算・勤怠管理システムと連携することで、通勤手当の円滑な管理が可能になります。
ご興味のある方は、こちらからお問い合わせください。
資料はこちらからダウンロードいただけます。